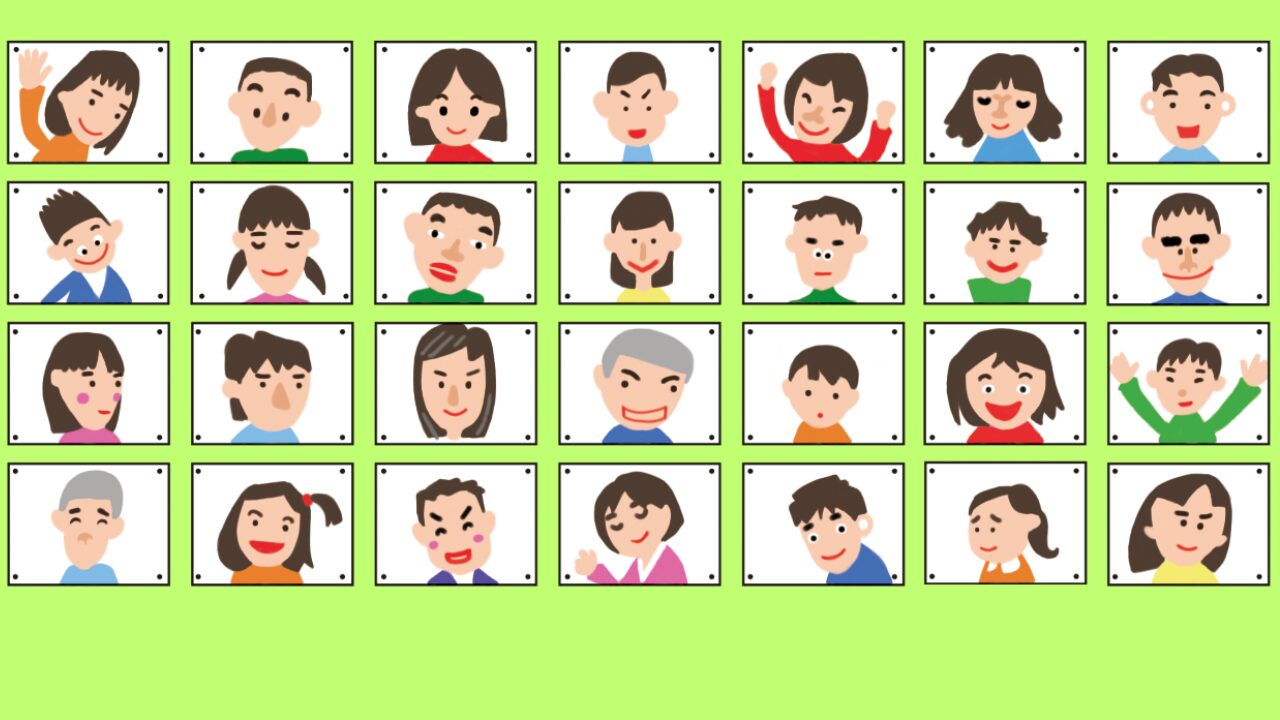夏休みが終わる季節にいつも思い出す出来事がある。
あれは小学校四年生のときだ。
小林くんといって、運動ができて明るく、クラスでムードメーカー的な存在だった。
その彼が一学期終了とともに転校することになった。
終業式にクラスでお別れ会をして、特に仲の良かった子たちは、
夏休みに入ってすぐに引っ越す小林くん一家を見送りにいったという。
クラス編成は三年生からの持ち上がりだったので、みんな仲が良かった。
四年生の夏、クラスメイトがひとり転校していなくなってしまった、
子どものころの小さな別れのひとつ、になるはずだった。
だが小林くんは転校先の学校で二学期を迎えることなく、
親戚たちと海へ遊びに行ったとき、水難事故で命を落とした。
夏休み明けにクラスメイトからそれを聞かされた私は半信半疑だったが、
ホームルームの時間に先生の口から聞かされてショックを受けた。
ニュースにもなっていたらしいが、大きくは取り上げられなかったので、
私と同じように気づかなかった友人もたくさんいた。
私は彼と特別仲が良かったわけではなかったが、お喋りしたことは何度もあるし、
学習発表会などで同じ班になった時は一緒に作業をしたりと思い出は少なくなかった。
一学期の図工の時間に描いた、自画像が教室の後ろに貼り出されていて、
その中には小林くんの絵もあった。
クラスの意見で、四年生のあいだは絵を撤去しないでおこうと決まった。
が、数日経ってから、クラスメイトたちがちょっとした事故で怪我をすることが多くなった。
最初は小林くんと仲の良かった子たちが、階段から足を踏み外したり、体育の時間に鉄棒から落ちて、
打ち身や捻挫、ひどいときは交通事故に遭って骨折などの大怪我をすることもあった。
それがほかのクラスメイトたち、果てはほかのクラスの子達にまで及びはじめ、
『最近は我が校で事故が多いです、みなさん気をつけてください』
全校集会で校長先生が注意喚起をするほどになったのだ。
事故にあった子たちは、みんな口を揃えて、
「階段で誰かに突き飛ばされた」
「歩いていたら足首を掴まれたような気がして転んだ」
「耳元で誰かの声が聞こえて気をとられた」
と、証言した。
だがそれが小林くんの仕業だとは、誰も気づいていない――私を除いて。
最初に気づいたのは二学期が始まって数日経ったときだ。
教室に貼り出されてあるみんなの自画像。
小林くんの絵が妙に浮いて見えたのだ。
そのうち周囲を黒い靄が覆いはじめ、
絵の中の表情が歪み始めた。
ひどく邪悪で気味の悪い顔だ。
だけどそれが視えているのは私だけだった。
私は人には視えないものが視えたり聞こえたりする体質だった。
もっと幼いときは周りに人にそういうことを話して、怖がられたり気味悪がられたりした。
その存在に『視えていること』を気づかれてはならない、関わり合いになってはならない。
そしてそれを周りの友達に話したりしてもいけない。
私の体質に気づいた母に何度もそう言い聞かされた。
母も子どものころから『人ならざるもの』が視える体質だったのだ。
私は母からその体質を引き継いだということになる。
ある日、忘れ物をして教室へ取りに戻ったことがある。
陽はかなり傾いていて薄暗く、誰もいない教室はしんとしていた。
忘れ物を机の引き出しからカバンに入れ、教室を出ようとしたとき。
ゾクッと背筋に悪寒が走った。キィン、と不快な耳鳴りがする。
はっとして振り返ると、すぐ後ろに黒い人影が立っていた。
それは壁に貼ってある絵から伸びた、長く黒い煙のようなものと繋がっていた。
つかみかかろうとしていた腕を払いのけると微かな手応えがあった。
相手が驚いたように立ち尽くしている。
「小林くん?」
私は影に向かって言った。
黒い人影はなにも言わないが、たじろいだように後ずさる。
「みんなが怪我をしてるの、小林くんのせいだよね」
尋ねても反応はないが、動揺しているのはわかった。
「みんな仲がいい友達でしょ、どうしてそんなことするの?」
ぶるぶる、と小さく影が震えて絵から伸びた煙に引っ張られるように移動していく。
「待って!」
だが影はどんどん薄くなり、絵の中に吸い込まれるようにして消えた。
その直後、私は吐き気とめまいに襲われ、その場にしゃがみ込んだ。
その後気を失っていたらしく、見回りの先生に発見されて保健室に運ばれた。
保健の先生に「救急車呼ぶ?」と言われたが、首を振って母に連絡するように頼んだ。
母が来るまで迎えに来てくれ、家に帰ってから教室であった出来事を話した。
「きっと小林くんは寂しかったのね、だけどそれが、寂しい、戻りたい、なぜ自分だけ、みんなが羨ましい、憎い、になってしまったんだね」
「でも……あんなに明るくて優しい男の子だったのに」
「人はね、この世に思いを強く残しすぎると、生きている人に害を与えてしまうことがあるの、悪意があるなしに関わらずにね」
「小林くんは……悪いことだとわかってみんなに怪我をさせてるの?」
母はちょっと困ったように笑うと、
「それはわからない……でも理沙が『どうしてそんなことするの?』って聞いたあとに襲うのをやめたんでしょ、まだ『悪霊』にはなっていないと思う」
まだ悪霊にはなってない……だけどなりつつあるんだ。
私は小林くんの明るくていい子だった生前の姿を思い出して悲しくなった。
「……どうすればいい?」
「教室に貼っている絵が『依代』になっているんだと思う。その絵をなんとかすれば……」
「ヨリシロ?」
「小林くんはまだそこまで力が強くないから、絵がないと理沙やお友達に会いに来れないってこと……だから絵を専門家の人にきちんと処置してもらえば大丈夫ってこと」
首を傾げた私に、母は優しげに笑って説明してくれた。
「絵を……教室からなくせばいいの?」
「そうだけど……できる、理沙?」
母の悲しげな表情を見てわかった。
ほかの人たちには視えない存在。
私たちだけが視ることのできる存在、知ることのできる感覚。
そして……他人には決して理解されない、ともすれば怖れられ疎まれること。
学校や先生に申し出たところで解決するはずがないから。
私たちだけで……視える体質の人間がやるしかない。
翌日の放課後。
一緒に帰ろうという友達の誘いをのらりくらりとかわして、トイレで教室が無人になるのを待った。
先生の見回りに見つからないように、トイレを出て教室に向かう。
『気休めにしかならないけど』
母がそう言って持たせてくれたお守りを握りしめながら教室に入った。
絵の前に立つ。
あいかわらず小林くんの絵は不穏に歪んで見える。
手を伸ばすとビリビリと静電気のような空気の壁を感じる。
三半規管がぐらぐらと揺れ、吐き気が込み上げる。
ぐっと歯を噛み締めて、素早く押しピンを抜き取って、小林くんの自画像を外した。
『ナニスルンダヨ、越嶌』
小林くんの声。
耳元で聞こえる。
振り切るようにして自画像を丸めて握りしめ、教室を出ようとした。
『ヤメロヨ、ナンデコンナコトスルンダ』
なにがあっても応えないで、相手にしては駄目。
母の言葉を反芻し、前だけを見てドアに手をかける。
開かない、鍵はかかっていないはずなのに。
『越嶌、エヲモドシテクレヨ、デナイトボクハココニコレナインダ』
グッと手に力を入れた。
わずかにドアが開く。
開けられないわけじゃない、もっと力を加えれば……!
体重をかけるようにして体を傾ける。
ギギ……とドアが開いていく。
背後に誰かが立つ気配がし、肩に手をかけられた。
『越嶌、トモダチダロ、オレヲモドシテクレ』
はあッ、と大きく息をはいた。
「そうだよ、友達だよ、だからこれ以上小林くんにここにいて欲しくないの!」
『ナンダッテ?』
「これ以上ここにいたら友達でいられなくなってしまうんだよッ!」
ふっとドアを固定する力が弱まった。
ドアを開け、教室を転がるように飛び出した。
廊下を走る。
先生に見つからないように祈りながら。
『越嶌アァァァァァ!』
背後から、いや、握りしめた絵から絶叫が聞こえた。
歯を食いしばって、涙を流しながら走った。
校門の前に車が停まっている。
母が私の姿をみとめて手を伸ばした。
「理沙! お母さんに渡して!」
リレーのバトンのように絵を手渡した。
母は眉間に皺を寄せて寄り合わせた紐のようなもので絵をぐるぐる巻きにすると、
「理沙、もう大丈夫、家に帰ってなさい」
それだけ言うと車を発進させて、あっというまにスピードをあげて走り去った。
私は息を乱してそれを見送った。
涙が止まらなかった。
あの日、母はちょっと疲れた顔で家に戻って来た。
「よくやったね、偉かったよ」
母はしっかりと私を抱きしめた。
私はまた泣いた。
小林くんの絵、どうなったの?
私が尋ねると、
「理沙はいま知らなくてもいい、もし知る必要があったら話すから」
そう言っただけだった。
翌日、小林くんの絵がなくなっていることがちょっと騒ぎになったが、
あまり問題にはならなかった、と思う。
よく覚えていないけど、絵がなくなったのと頻発していた事故が収まったことで、
学校も生徒もなんとなく察したのかもしれない――誰ひとりとしてそんなことは口に出さなかったけれど。
母があの絵をどこへ持っていったのか、どう処理したのか知らない。
そしていまも聞かされていない。
いつか聞く機会があるのだろうか。
あのとき知ったのは、生者と亡者はかかわってはいけないのだということだ。